 |
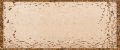 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
福島第1原発で爆発 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
炉心溶融(メルトダウン)の可能性 |
|||
炉心溶融(メルトダウン)が進行すると、溶けた核燃料が、圧力容器の底に溜まり、その熱によって圧力容器の底の材料を溶かしてしまい、格納容器内に溶融した核燃料が落ち、その落ちた核燃料が格納容器内の水と反応して水蒸気爆発を起こしてしまう可能性があります。 メルトダウンした場合は、原子炉圧力容器の底が抜けた状態になっています。その状態で格納容器の中で水蒸気爆発しますので、最悪の場合は、爆発の威力で原子炉圧力容器、格納容器などが破損され、大量の放射性物質が周囲に拡散してしまいます。 なので、あらゆる手を尽くして、炉心溶融(メルトダウン)の進行を抑えることが必要であり、最も重要なことになります。 今回の原発事故では、1号機と3号機が水素爆発を起こして建屋の上部を壊しました。4号機の原子炉には検査のために核燃料が入っていなかったのですが、爆発して建屋が損壊しました。保管プール移動してあった使用済みでない核燃料は、使用済みとは比較にならないほど元気だろうことが推測できますので、たぶん4号機も水素爆発によるものだと思います。 建屋は水素爆発であの状態になったのですが、建屋内部にある格納容器の構造は大きく違います。メディアの報道を聞いていると、格納容器の認識が違っているような感じを受けましたので、格納容器の構造について、少し書いておきます。 ただし、私自身は原発の設計にも建屋建築にも関わったことはありません。私のサイトの別のコンテンツ「建築の豆知識」を読まれたことがある方ならご存知だと思いますが、私は都市計画や大規模開発の企画・構成などの仕事をしていますので大手ゼネコンとは付き合いがあります。 私がしていることは、グランドデザインや行政などとの調整が主なのですが、大規模建築物をプランする都合上、建築物の耐震構造について話すことがあります。たまたま、雑談の中で原発の構造の話しになった時がありましたので記憶に残っていたのですが、聞いた時は、その構造のすごさに、さすがに原発だなと驚いたくらいでした。 原発については細かい施工方法を書けないので、ざっくりとした書き方になりますが・・・ 格納容器は、フラスコのようになっています。その外側のSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)は格納容器を守るように出来ていますが、均等な厚みで作ると円柱状になりませんので、どうしても厚い部分と薄い部分が出来ます。SRCの部分を含めると、壁厚が薄い所で2mくらい、厚い所で4m以上になってしまいます。 また、その部分は、内面になる鋼鉄の格納容器の部分を省いて、その外側に、鋼板(10cm前後)・鉄骨鉄筋コンクリート(80cm以上)・鋼板(50cm前後)・鉄骨鉄筋コンクリート(80cm以上)という具合に、鋼板とSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)をサンドイッチ状にして作ってありますので、簡単には壊れません。保管プールの床や壁にしても、プールと言えども核燃料を入れる場所になりますし、建屋の上部にありながら水が1400トンくらい入るプールですから、同様に頑丈な作りになっています。 ちなみに、例えば、鋼板の厚みが50cm(500mm)と言うのは、20mmの厚みの鋼材なら25枚、又は、25mmの厚みの鋼材なら20枚重ねて、50cm(500mm)にしてあるような状態です。ステンレス、鉛、鉄など、いろいろな材質の材料を組み合わせ、内部の格納容器を守るように、放射線を通過させないように、耐震強度があるように、計算して厚みが決めてあります。 このように、格納容器は、外部のSRCの部分も含めると、壁面(底面)が約2m〜4mの厚みになり、中身が鋼鉄、鉄骨、鉄筋、コンクリートで出来ている状態です。通常の建物からでは、想像がつかない程頑丈な構造になっていますから、ある程度の衝撃には耐えてくれるようになっています。 ただ、福島第1原発は、1号機が40年前と古いので、新耐震ではなく、以前の耐震基準で出来ています。ここまで頑丈でないかもしれませんが、物は原子炉を守る格納容器です。万が一にも問題があっては困りますので、当時の技術を結集して出来ていると思います。 壊そうと思っても、どうやって壊せば良いのか悩むような代物ですから、もし、これが壊れるような状況でしたら、中にある圧力容器も原子炉も無傷ではいられません。結果、相当量の放射性物質が拡散されますので、現状のような放射線量では済んでいません。 それに比べて、格納容器の上部にある建屋部分は、ただの箱ですから、そこまで頑丈には出来ていません。言い方を変えると、(地震や津波の影響でも原子炉建屋はそのままの状態を保っていたように、通常の建物よりは、はるかに頑丈ですが)建屋は、格納容器や保管プールの底床や壁に比べて弱くなっています。水素は軽いので建屋上部に溜まりますし、爆発すると、その爆心に近い部分が壊れやすいですし、どうしても、弱い部分が大きく損傷しますので、今回の様に建屋上部の弱い部分が破損します。
ですが・・・ 格納容器内で大規模な水蒸気爆発が起きた場合は、原子炉、原子炉圧力容器、格納容器がどうなるか見当もつきません。もし最後の砦の格納容器が破損に至らなくても亀裂が入っただけでも、隙間が出来てしまいます。隙間があると、そこから拡散してしまいますので、放射性物質の大量拡散を抑えれなくなります。 制御棒が差し込まれ停止していますので、臨界の可能性は無いと思いますが、停止して間もない時期に電源を喪失し冷却が出来なかったため、燃料集合体が露出し高熱を維持しているので、メルトダウンの可能性はあります。可能性がある以上は、その可能性を否定しなければいけませんから、最悪の事態を想定して、手を打っていかなければなりません。放射性物質の大量拡散につながる可能性があるメルトダウンの進行は、何としてしてでも食い止めなければいけません。 津波の影響で非常用ディーゼル発電機が水をかぶったことで電源喪失に陥り、原子炉の冷却が出来なくなり、核燃料の余熱で中の水が急速に蒸発し、内部圧力が上がってしまいました。電源車の動力で水を入れようにも内部の圧力が高すぎて注入出来なくなったので、弁を開放して、内圧を下げ、水の注入を可能にしたのは、なにより、核燃料の冷却のため、メルトダウンの進行を抑えるための行為ですから、結果的に水素爆発が起きてしまいましたが、弁開放はやむを得ない状況でした。 その後もなんとか海水を入れて原子炉内の燃料の冷却を続けていますが、1号機〜3号機の原子炉では、核燃料が露出した状態で最低限の冷却を続けていますので、燃料が破損した炉心溶融になっていると推測できます。外部電源を繋いだとしても、地震や津波、水素爆発によって、原発は損傷を受けています。どの程度の機械(ポンプなど)、設備(水回り、空調、電気)が使えるかは不明ですので、状況は、かなり深刻です。 福島第1原発の現状を考えると、メルトダウンによって多量の放射性物質の拡散を防ぐためには、原子炉内の核燃料を冷却しなければならない。原子炉内の圧力が上がり過ぎると思うように水が入れれず冷却できない。冷却するためには、原子炉内の圧力を下げる必要があるため、弁を開放してガスを放出するのは、止むを得ない状況です。 弁を開放すれば、放射性物質の拡散はありますが・・・ それをしないで、もし原子炉圧力容器や格納容器が破損したら、比較にならない量の放射性物質拡散になってしまいます。 3月23日に1号機の炉内温度が一時的にでも400度と設計温度の302度を上回り、かなり高温になっていますから、核燃料自体の温度も高く、融けて炉心溶融が進行していると推測できますし、原子炉自体がかなり不安定な状態になっていると思います。2号機は原子炉と圧力抑制室と保管プール、3号機は原子炉と保管プール、4号機は保管プールと、それぞれが大きな問題を抱えています。 安全停止までには、しなければならないことが沢山ありますが、問題を抱えている原子炉が4つもありますから、まだまだ予断を許さない状態が続いていきます。 |
|||
|
使用済み核燃料保管プールへの放水(注水) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自衛隊、警察、消防、東電及び協力会社などによる3号機や4号機の使用済み核燃料保管プールへの放水(注水) 3号機の保管プールへ放水(注水)
4号機の保管プールへ放水(注水)
25日以降も生コン圧送機を使い4号機の保管プールには随時注水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力緊急事態・時系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・海が白い壁、ポンプ次々流され…地震当時の原発 - 読売新聞 ・周辺の津波 14メートル以上の可能性 - 毎日新聞
・原子力災害対策特別措置法(平成十一年十二月十七日法律第百五十六号) ・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規正法)(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島第1原発の各原子炉の状況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子炉や圧力容器、また格納容器や格納容器を守る躯体(構造材)は耐用年数が長いですが、空調や循環系に使う配管などは、躯体ほど耐用年数は長くありません。言い換えると、格納容器はある程度の耐力がありますが、配管は格納容器やその周囲にある躯体と比べると、どうしても耐力は落ちてしまいます。 長い時間炉心(核燃料)が露出した状態の後で水素爆発が起きていますし、爆発によって建屋の上部が崩壊するくらいの威力でしたから、建屋だけでなく配管設備が影響を受けていたとしても何の不思議もない状況です。また、炉心を露出した状態が長く続き、炉心溶融にもなっているでしょうし、緊急避難とは言え、海水を使って核燃料を冷却していました。 通常運転ではない状態が長く続いたので、何が起きても不思議ではありませんが・・・ タービン建屋において、放射能汚染された水がたまっていたのが分かりました。かなり濃度も濃く、本来なら燃料棒の中にしか存在しない放射性物質も検出されています。 これらのことなどにより、タービン建屋では、溶融した核燃料から出た放射性物質に汚染された水が、何らかの原因で損傷した配管から流れ出た可能性が高いとみて、「水回り配管損傷の疑い」と入れてあります。
追記 2号機のタービン建屋の地下を調査した際、線量計が振りきれてしまい、1シーベルトどころか、どれだけの数値か分からない状態ですし、溜った水を調査した結果、高濃度で放射性物質が検出されています。本来なら燃料棒の中に存在する放射性物質が、次から次へと漏れ出ている状況ですから、炉心溶融が進行しているのも、配管損傷もほぼ間違いないようです。3号機も、400ミリシーベルトから750ミリシーベルトへと、倍近く濃くなっていっていますから、同様なことが言えます。 これだけ放射線量が高くなってくると、例えば、1シーベルトの環境ならば1時間の4分の1のたった15分で年間被曝量の限度である250ミリシーベルトに到達してしてしまうなど、一人が作業できる時間が極端に短くなってしまうため作業が思うように出来ず、作業効率は格段に落ちてしまいます。同時に複数の炉で、炉心溶融、配管損傷(汚染水漏れ)、高放射線量などと、大きな問題がいろいろと起きていますから、かなり深刻な状況です。
追記 タービン建屋の地下と繋がっている作業用トンネル「トレンチ」でも大量の汚染水が見つかったようですが、1〜3号機を合わせると、多くて1万3000トンくらいになるようです。放射能に汚染された水ですが、地下にあるその汚染水を除去しないことには、冷却装置の復旧が出来ません。その汚染水を仮にでも収納できるタンク(容器)が少なく困っているようですが、何としてでも汚染水を除去して冷却装置を復旧させ、原子炉を冷却しなければならないのが現状です。 汚染水ですから最終的には除染しなければいけないですが、優先順位からすれば、今、その作業をすることはありません。現状では、その汚染水を仮にでも収納出来れば良いので、陸上でのタンクが足りなければ、海上で用意したらどうかと思います。仮に現在1万3000トンあり、今後の原子炉冷却によって、漏れて汚染水が増えていったとしても、とりあえず、10万トンくらい入る容器を用意しておけば急場は凌げると思います。 陸上では、10万トンの水が入る容器なんて、作るのが大変で工期もかかりますから、すぐに用意できませんが、海上でならば、曳航に多少の日にちは要しますが、陸上とは比較にならないくらい早さでその大きさの容器が用意できます。 陸上ではなく、海上でなら割と早く用意できる10万トンの容器とは・・・ 10万トン級のタンカーのことです。 原油の輸送などに使っているタンカーは、容器(タンク)ですから、10万トン級タンカー1隻を福島第1原発の港に接岸できれば、そのタンカーを水の仮置き場でですが、10万トンの容器として使うことができます。 タンカーのデッキの位置は高いですが、仮設で足場を組んでいけばホースの通り道も確保できますし、タービン建屋の地下と作業用トンネルの「トレンチ」とは繋がっているようなので、外部にある全部の立抗(11ヶ所?)からポンプを入れて排水する方法も可能だと思います。2号機のように高濃度の放射線量の環境下では、中で作業をするより外での作業の方が被曝量は少ないと思いますし、ポンプの能力が高いのを多く用意すれば、早く排水できると思います。なにより、容器の容量が大きいですから、当分の間は、容器の心配をしなくても済みます。 福島第1原発は危機的状況でやらなければならないことも多いのですが、同時に、少しでも早く放射性物質拡散を止めなければならないという時間との戦いでもあります。通常では、こんなことは考えませんし、発想も突飛かもしれませんが、現存する巨大な容器で福島第1原発に移動可能な物と言えばタンカーくらいしかありません。今のような状況では、タンカーを仮の容器に使うという考え方も「有り」なような気がします。 1隻でいいから、廃船間近で中身が空になっている10万トン級タンカーを日石や出光あたりが持っていないかなぁ・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島第1原発の各原子炉の復旧状況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1〜4号機は原子炉建屋や圧力抑制室などに損傷を受けているため、仮に原子炉や保管プールで核燃料が冷温停止状態になったとしても放射性物質が漏れ、多少なりとも拡散は続きます。何らかの方法で放射性物質が拡散しないように閉じ込める必要がありますので、1〜4号機については最後の欄に「放射性物質の閉じ込め」の項目が設けてあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
